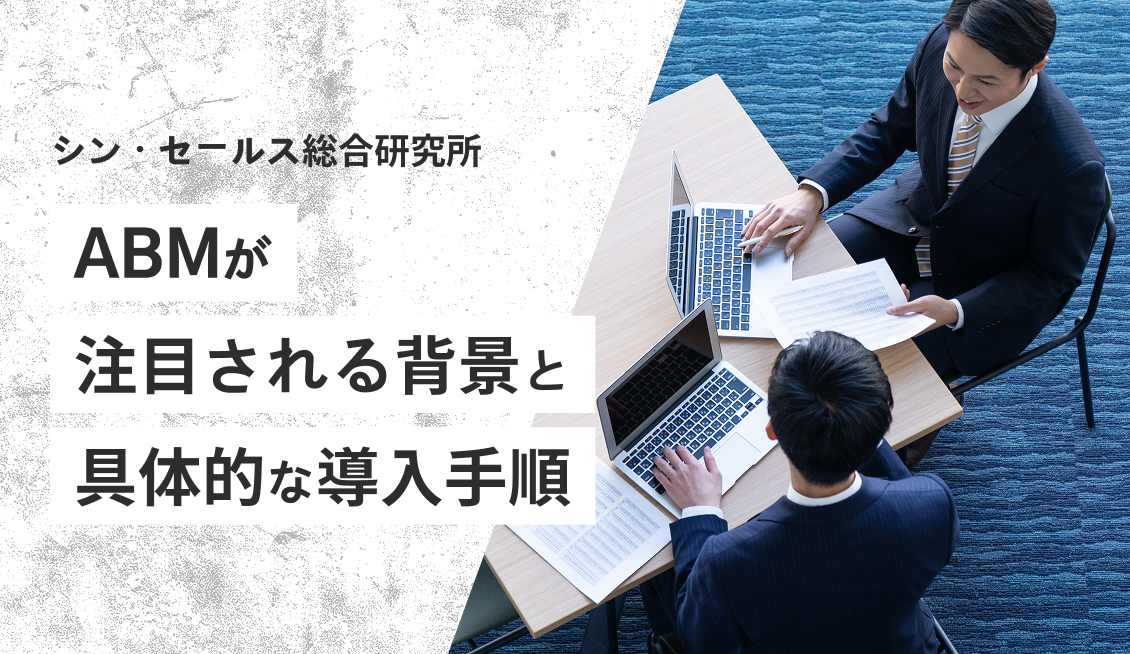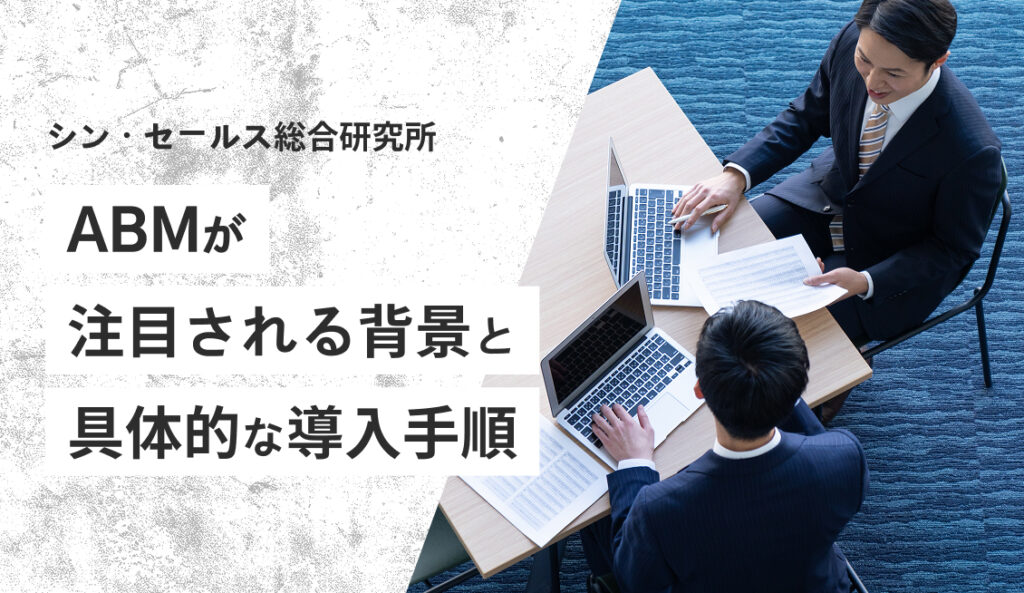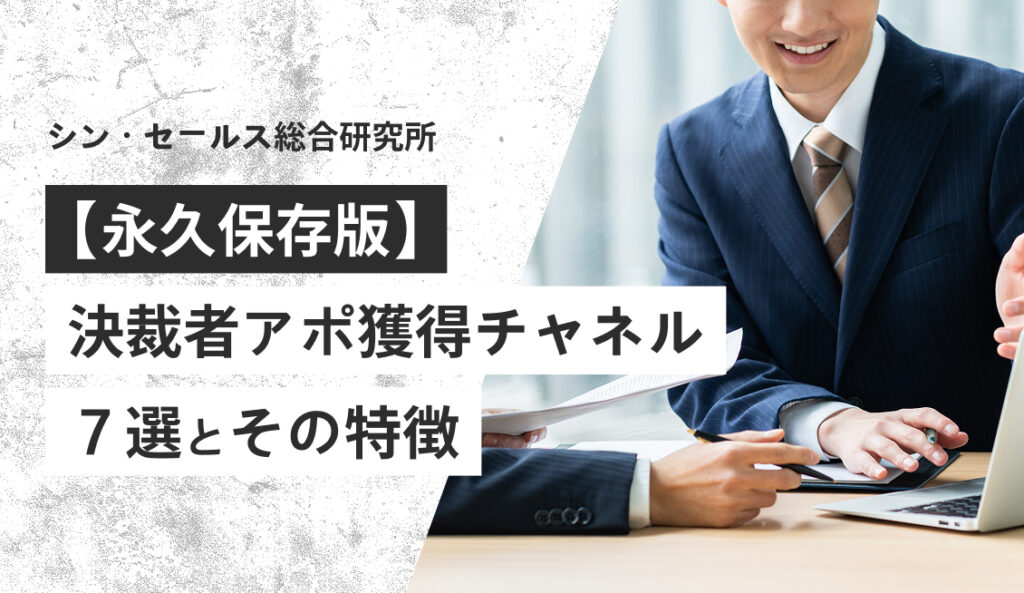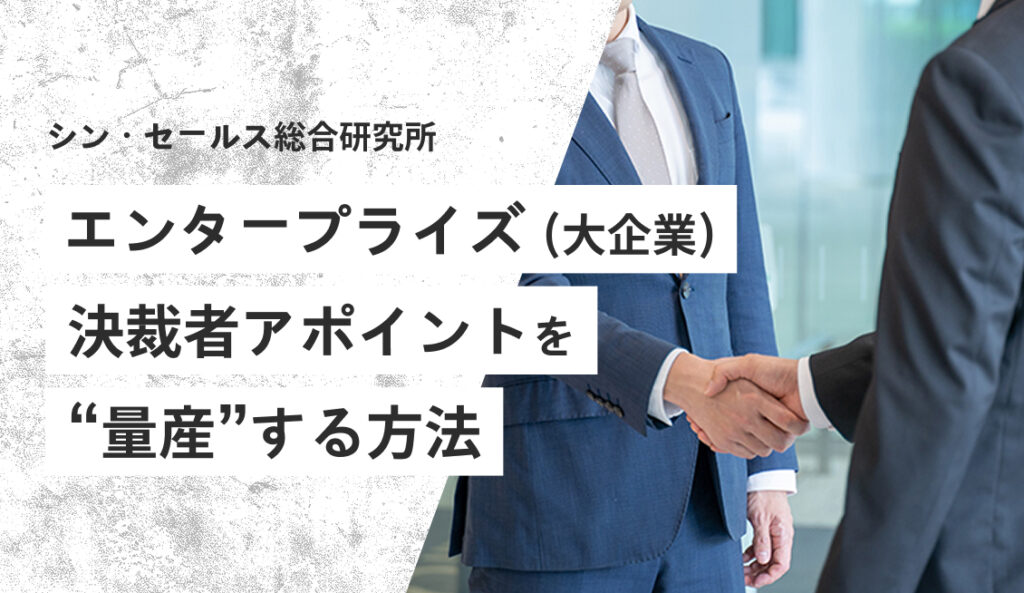はじめに
ABMは「特定の企業(アカウント)を狙い撃ちし、その企業が抱える課題やニーズに合わせて深くアプローチするマーケティング手法」のことを指します。従来の“マスマーケティング”や“リードを大量に集める”発想とは対極にあり、あえてターゲットを絞り込むことで、より質の高い商談や受注率の向上を狙うのが特徴です。直近弊社にもABM施策に関するご相談が増えているのですが、これはBtoB市場で競合が激化し、大手企業やハイレイヤーの顧客にフォーカスする必要が高まっていることが背景にあります。
同時に、ABMが流行している理由としては、営業やマーケティングのデジタル化が進み、企業や担当者の情報を得やすくなった点も大きいと考えられます。以前であれば、大手企業内部の構造を調べたり、個別の部長クラスに辿り着くのは容易ではありませんでした。しかし、SNSの台頭や外部データの充実によって、比較的スムーズに社内の主要キーマンを探し当て、個別の戦略を組めるようになったのです。
とはいえ、ABMは従来の一括アプローチよりもはるかに工程が多く、担当者の力量に左右されやすい手法であるため、実際に使いこなせている企業はまだ少数と言えます。「難しいからこそ、今取り組めば大きな差別化ができる」と見る向きもあり、ますます注目が集まっているわけです。
そこで本記事では、ABMの基本的な仕組みからメリット、実際の手順や成功のためのコツまでを整理し、これからABMを導入してみたい企業や担当者に向けたガイドとしてまとめました。
ABMのメリット
ABMが注目される理由はさまざまですが、代表的なメリットとしては以下の三つが挙げられます。
LTV(顧客生涯価値)の向上
特定の企業と深い関係を築くことで、一度の受注に留まらず、長期的なリピートや追加発注が期待できるようになります。大手企業の場合、導入が決まれば契約金額自体が大きいため、LTVの向上が企業収益に直結しやすいと言えます。
ROI(投資対効果)の改善
大量のリードを集める施策は一見コストが安そうに見えますが、結果的に質の低いリードが多く集まり、営業リソースを浪費してしまうことが少なくありません。ABMでは「最初から狙うべき企業に焦点を当てる」ため、無駄打ちが減り、時間や人件費を効率よく使えるようになります。
Tierの開拓
従来の手法ではアクセスが難しいとされていた大手企業や役員クラスにも、ABMであれば「徹底した事前リサーチ」や「個別の提案」を通じてアプローチが可能です。結果として“最上位のTier”に分類される企業を開拓できれば、その後の
ABMが向いている企業
ABMは全企業に向くわけではなく、以下のような条件を満たす場合に特に効果が大きいと考えられます。
- LTV(顧客生涯価値)が高い:一定規模以上の企業を顧客としており、単価が大きく、長期取引の見込みがある
- 大手企業を開拓したい:Tierを引き上げたい、あるいは今後さらにブランド価値を上げたいという企業
- ターゲットが狭い:不特定多数ではなく、特定の業種・規模に絞ったビジネスを展開している場合、ABMが最適な手法となりやすい
ABMの手順
ABMにはいくつかのステップがあり、一気にすべてを完璧に行うのは簡単ではありません。以下では、おおまかな流れを解説します。
1. ターゲット選定
最初に、「どの企業を重点的に攻めるか」を決めます。企業名だけを洗い出す段階もあれば、人物名まで特定することもあるでしょう。特にAIプロダクトやSaaSなど、導入に大きなコストや社内調整が伴うサービスの場合、事前に組織図を調べたり、既存顧客の類似企業を探したりするケースが多いです。
ここで「人物名までリストアップするのか」「企業名だけで進めるのか」は、かけられる予算や工数とのバランスが重要になります。完璧に作ろうとしすぎると時間ばかりが過ぎて実働が遅れ、“テストセールス”的な要素が後回しになってしまうため、社内での期待値や締め切りを踏まえて決めるべきです。
2. リストアップ
ターゲットを選んだら具体的にリスト化を進めていきます。最低限、企業名・電話番号・ホームページURL・ターゲット部署名などを揃え、余裕があれば人物名や所在地、想定課題なども書き加えると良いでしょう。ただし、これもやりすぎると“リスト作り”が終わらないままになるリスクがあるため、“必要十分な項目”を見極めることが大事です。
また、“仮説としての課題・ニーズ”を一緒にメモしておくと、後のアプローチで「相手は○○を悩んでいそうだから、こういう話をしよう」という作戦を立てやすくなります。
3. チャネル選定
ターゲットのリストが揃ったら、今度は「どの手段でアプローチするか」を考えます。コール、フォーム送信、手紙(レター)、SNS(LinkedIn・Facebook・Xなど)、リファラルなどが候補になります。
人物まで特定している場合は、手紙やSNSを活用した“個別アプローチ”が威力を発揮しやすいでしょう。大手の部長や役員クラスに電話をかけるのは難易度が高いことも多く、むしろSNSやレターで“直接”コンタクトしたほうが通りが良いケースもあります。ここで企業文化や業界の慣習なども考慮しながら最適なチャネルを選択することが重要です。
4. マルチチャネルアプローチ
ABMではターゲット企業が限られている分、シングルチャネルだけで済ませるのはもったいないという考え方が基本にあります。SNSからアプローチできるならSNSを先に試み、それで反応が薄ければレター+コールを組み合わせる、というように複数の手段を用いて相手の反応を得る確率を高めるのが効果的です。
「どれを先に使うか」は相手の性質や自社コスト、速度感次第ですが、概して、
- 接点がある場合(既存の繋がりがある人)
- その接点をフルに活かして紹介やリファラルで持っていく
- 接点が全くない場合
- まずはコストとスピードの観点からSNSを試す
- SNSで ダメならレター+コール
- そこでもダメなら時間を空けて再アプローチ
こうした流れで粘り強くアプローチすることが多いです。
ABMを成功させる上でのポイント
ABMが流行している一方で、現場レベルで「うまくいかない」という声も多く聞かれます。その理由を幾つか挙げると、以下のような課題が浮かび上がります。
ABMの”落とし穴”を適切に把握し、対策する
一見すると「特定企業を狙うだけだから簡単じゃないか」と思われがちですが、ABMには次のような難しさがあります。
長期戦になってしまう
短期的に成果が出る手法ではなく、中長期の時間軸で動く必要があるため、社内の関係者や上層部がその点を理解していないと腰折れしがちです。
運用リソースが不足している
ターゲット企業一社ごとに深いコミュニケーションが必要となり、担当者に掛かる負荷が高くなります。さらに、マーケティングだけでなく、フィールドセールスなどの現場部隊にも高いスキルが求められるため、部分最適では成果が生まれにくいです。またABMは1~2人の担当者だけに押し付けても成功しにくいと言われます。営業・マーケ・カスタマーサクセスが一体となり、「この企業はこういう課題があるはずだから、こういう提案で攻めよう」という共通認識を持つ必要があります。そのうえで、誰がどのタイミングでフォローを担当するのかを明確化し、情報が滞留しないようにするのがポイントです。
フィールドセールスの品質が低い
いくらインサイドセールスなどでターゲットと接点を作っても、商談の場で適切に提案できる力がなければ実際に受注まで至らないのが実情です。意外とこの点が抜け落ちている企業が多く、最終的に「アポは取れたが受注に繋がらない」という壁にぶつかります。
まとめ
ABMが流行している背景には、BtoB商材の高度化や大企業での意思決定プロセスの複雑化などがあり、従来の“一括で大量リード獲得”の手法だけでは大きな案件を取りこぼすリスクが高まっているという現状があります。とはいえ、ABMは個別企業へのカスタマイズと粘り強い接触が不可欠で、しっかり体制を作らないと中途半端なまま頓挫してしまいがちです。
- ターゲット選定で“誰に本当に売りたいのか”を明確にする
- リストアップやアプローチチャネルを丁寧に選び、マルチチャネルで試行錯誤する
- 社内連携やPDCAを回し続けて、個別企業との関係性を徐々に深める
これらを地道に実行していけば、大手企業の部長や役員、急成長スタートアップのCXOなど、通常は時間や距離のある層とも具体的に商談を進められるようになります。難しいからこそ“できている企業が少ない”ABMで差別化を図り、高額かつ長期的な収益を見込める大手企業案件を成功させる一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
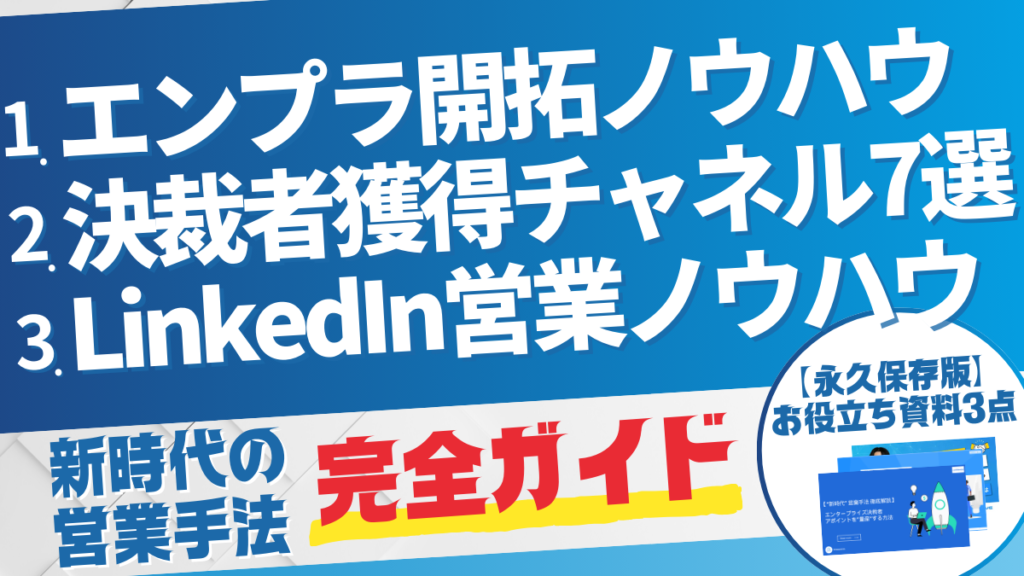
新規開拓に活用できる資料3点セットをダウンロードする
- 【”新時代” 営業手法 徹底解説】エンタープライズ決裁者アポイントを”量産”する方法
- 【永久保存版】決裁者アポ獲得チャネル7選とその特徴
- 【国内初!】「LinkedIn」を活用した、新時代のアウトバウンド営業とは